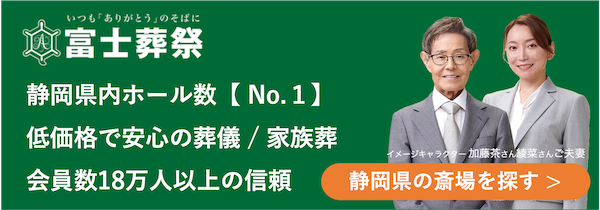BLOGS
葬儀・家族葬ブログ

葬儀の知識
静岡の通夜・葬儀のしきたりはある?昔ながらの作法を紹介
こんにちは。静岡の葬儀社 富士葬祭です。
冠婚葬祭には地域特有のしきたりがある場合も多いですが、近年では地域による違いが少なくなり、全国的に統一された形式が一般的となっています。
静岡県でも、現在は全国で一般的な通夜・葬儀のしきたりと違いはありません。
ただし、地域によっては昔ながらの風習や文化が大切に受け継がれているところもあります。
そこで今回のコラムでは、静岡県の昔ながらの葬儀のしきたりについて解説します。
通夜・告別式でのしきたりや、静岡独自の風習など、地域ごとの特徴をご紹介しますのでぜひご覧ください。

目次
静岡ならではの葬儀のしきたりはある?
葬儀は、日本全国でそれぞれに地域ごとの異なるしきたりがあります。
しかし、冒頭でもお伝えした通り、現在は全国的にしきたりに大きな違いがあるケースは少なくなってきています。
静岡県も同様で、基本的には全国に共通する一般的なしきたりと違いはありません。
そのため、「静岡の葬儀だから…」と身構えて参列する必要はありませんよ。
ですが、地域によっては、昔ながらのしきたりや伝統が残っていることもあります。
東西に長い県域を持つ静岡県も、地域によって異なる葬儀のしきたりがありました。
通夜の形式や食事の習慣、出棺時の作法などに、東部・中部・西部それぞれの地域で独自のしきたりや文化が見られます。
地域ごとの違いを知っておくと、馴染みのないしきたりに出会ったときにも対応しやすいものです。
静岡での葬儀に参列する際は、次にご紹介する昔ながらのしきたりについて、知識を持っておくと安心です。
静岡のお通夜のしきたり
葬儀の前日に執り行うお通夜では、次のようなしきたりが静岡県特有のものとして挙げられます。
流れ通夜
静岡県西部の遠州地方では、「流れ通夜」と呼ばれる形式の通夜式が見られます。
開始時刻が定められている一般的な通夜式とは異なり、流れ通夜では遺族・親族以外の一般参列者に対しては明確な開始時間が決まっていません。
一般的には18~20時などの2時間程度が設定され、一般参列者はその間であればいつでも弔問できます。
一般参列者は時間内の好きなタイミングで訪れ、焼香をし、遺族とあいさつを交わしたら、着席せずに帰宅します。
読経などの宗教儀礼は、一般参列者の弔問時間前に遺族や親族のみで執り行なっており、通常、一般参列者は参列しません。
通夜祓い(つやばらい)
通夜式終了後には、遺族・親族・参列者・僧侶などで「通夜振る舞い」と呼ばれる会食をするのが一般的。
静岡県西部では、この会食は「通夜祓い(つやばらい)」と呼ばれます。
全国的には、通夜振る舞いに招かれた場合はひと口だけでも箸をつけるのがマナーとされていますが、静岡県では通夜振る舞いや通夜祓いは遠慮される方も多いといわれています。
静岡の葬儀のしきたり

静岡での葬儀の流れも、基本的には一般的なものと大きく変わりません。
しかし、作法や儀式、食べ物などには、静岡の地域ならではのしきたりや風習などが一部の地域で残っていることもあります。
昔ながらの静岡の葬儀の特徴的なしきたりをご紹介します。
引換券
静岡県西部では、葬儀の受付で香典を渡すと、葬儀後に行われる会食「精進落とし」の食事券や香典返しの引換券が渡されることがあります。
香典返しも当日に渡される「当日返し」が主流で、お渡しした香典はその場で開封して金額の確認がなされるケースもあります。
なお、精進落としに参加するのは遺族や親族、近しい知人が中心で、一般参列者は参加せずに帰宅するのが通例です。
仮門を通る出棺
静岡県の中部・東部では、出棺の際に「仮門」を通るという独特のしきたりがあります。
青竹や藁(わら)、葦(あし)、茅(かや)など、地域によってさまざまな素材で作られたアーチ状の門を設置し、そこを通って出棺します。
仮門は出棺後すぐに壊され、故人様の魂が元の場所に戻れないようにすることで、「迷わず成仏できるように」という願いが込められています。
祓い膳・忌中祓い(きちゅうばらい)
静岡県中部地域では、葬儀終了後の食事「精進落とし」を「祓い膳」や「忌中祓い」と呼ぶことがあります。
また、御前崎市周辺では、精進落としの際に「お淋し」と呼ばれる黒豆入りのおこわを振る舞うという伝統も。
これは、お祝いごとの際に食べる赤飯に対する「逆さごと」という意味合いを持つとされています。
前火葬
静岡県沿岸部の一部地域では、葬儀の前に火葬を行う「前火葬」の慣習が残っていることがあります。
前火葬の場合は、葬儀の祭壇には遺骨が安置され「骨葬」として葬儀が執り行われます。
三日の法要
静岡県西部の地域では、「三日の法要」という追善供養が行われることも。
これは死後3日目に行われる法要で、初七日法要と合わせて葬儀当日に繰り上げて「三日七日の繰り上げ法要」として執り行われることもあります。
三日の法要が行われる場合は、参列者は葬儀のお香典とは別に、三日の法要用として1,000~3,000円程度のお香典を用意するのが一般的です。
葬儀当日の納骨と宝冠
静岡県の沿岸部では、火葬された遺骨を葬儀当日に納骨する習慣があります。
納骨のために墓地に向かう遺族は「宝冠」と呼ばれる三角形の白い布や紙を額に付けます。
これは、浄土へとつながる白色であり、故人様の死装束の一部を遺族が身につけることで、故人様の魂を「あの世との境まで見送る」という意味が込められています。
葬儀の食べ物に関するしきたり
静岡県には、葬儀に関連する特徴的な食べ物のしきたりがいくつか存在します。
力餅
牧之原市周辺で葬儀の際に配られる、あんこや飴をまぶした餅。
かつての土葬時代、力仕事をする人々のために振る舞われたとされています。
縁切り餅
静岡県東部で葬儀の際に配られる、一口サイズの餅。
故人様との永遠の別れを象徴する「食い別れ」の儀式として位置づけられています。
浜降り
沼津市で、納骨後に親族が海岸や河原に集まり、位牌を囲んで食事をする習慣があります。
基本は静岡も他地域も葬儀のしきたりは同じ。昔ながらの風習も知っておこう
現在の静岡県の葬儀は、全国の一般的な葬儀のしきたりと変わりはありません。
しかし、地域によっては、昔ながらのしきたりや伝統が残っていることもあります。
葬儀のしきたりはそれぞれの地域で大切に受け継がれてきた独自の文化、風習です。
基本的には一般的な葬儀に参加するのと同じで、身構える必要はありませんが、その地域特有のしきたりに出会ったときは、それを理解し、敬意を持って対応することが大切です。
静岡県の葬儀は、富士葬祭におまかせください。
いざというときに慌てないためにも、葬儀場の見学や事前相談も承っております。