BLOGS
葬儀・家族葬ブログ

葬儀の知識
葬儀と友引の関係は?友引に葬儀を行う際の注意点と日程の決め方
こんにちは。静岡の葬儀社 富士葬祭です。
葬儀の日程を決める際、「友引の日は避けたほうが良いのだろうか」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
また、実際に葬儀を行うことになったときに、日程をどのように決めれば良いか迷われることもあるでしょう。
そこで今回は、友引と葬儀の関係について詳しくお話しし、葬儀の日程を決める際のポイントをご紹介します。
大切な方とのお別れの時間を心穏やかに過ごしていただくためにも、ぜひ参考にしてください。

目次
友引とは
友引(ともびき)とは、「六曜(ろくよう)」の一つです。
六曜は中国で生まれた占いが起源とされており、鎌倉時代末期から室町時代にかけて日本に伝わったとされています。
江戸時代末期頃から一般に広まり、現在でも冠婚葬祭の日程を決める際に重視される方が多くいらっしゃいます。
六曜には友引以外にも、先勝(せんしょう)、先負(さきまけ)、仏滅(ぶつめつ)、大安(たいあん)、赤口(しゃっこう)があり、それぞれに縁起の良い時間帯や悪い時間帯が定められています。
友引はもともと「共引」という表記がされており、勝負事において勝敗がつかず引き分けになるという意味がありました。
そこから変化していき、現在では「ともに引き合う」「友を引く」という意味から、災いが友人におよぶと解釈されるようになりました。
なお、「仏滅」などから仏教と関係があると思われがちですが、実際には六曜と仏教は関係がありません。
あくまでも中国由来の占いであり、迷信の一種とも考えられています。
友引に葬儀を行うことは可能
結論から申し上げると、友引に葬儀を行うことは可能です。
前述の通り、六曜と仏教には関係がないため、宗教的な観点から友引の葬儀が禁止されているわけではありません。
しかし、実際には友引に葬儀を行うことは避ける人が多いのが現状です。
その理由は、「友を引く」という意味から、「故人様が友人をあの世に連れて行ってしまう」という迷信があるためです。
この迷信により、友引の日に葬儀・告別式や火葬を行うのは縁起が悪いとされてきました。
一方で、お通夜については友引の日に行なっても問題ないとされています。
お通夜は故人様との別れの儀式ではなく、家族や友人などが集まって故人様を偲ぶ場という側面があるためです。
そのため、友引の意味である「友を引く」ということには当てはまらないと考えられています。
葬儀を友引に行う際の注意点
友引に葬儀を行う場合には、いくつかの注意点があります。
まず、友引を気にする参列者や親族がいる可能性があるため、事前の配慮が必要です。
迷信や風習を重んじる方もいるため、特に年配の方や地域の慣習には注意を払いましょう。
また、多くの火葬場が友引を定休日としているため、火葬ができないケースがあります。
友引の日は葬儀を避ける方が多いことから、地域によっては火葬場自体が休業している場合があるのです。
そのため、友引の日に葬儀を行いたい場合は、利用可能な火葬場があるかどうかを事前に確認しましょう。
さらに、友引の翌日は火葬場が混雑しやすくなります。
定休日明けということもあり、予約が取りにくくなる可能性があるため、早めの手配が大切です。
葬儀の日程の決め方
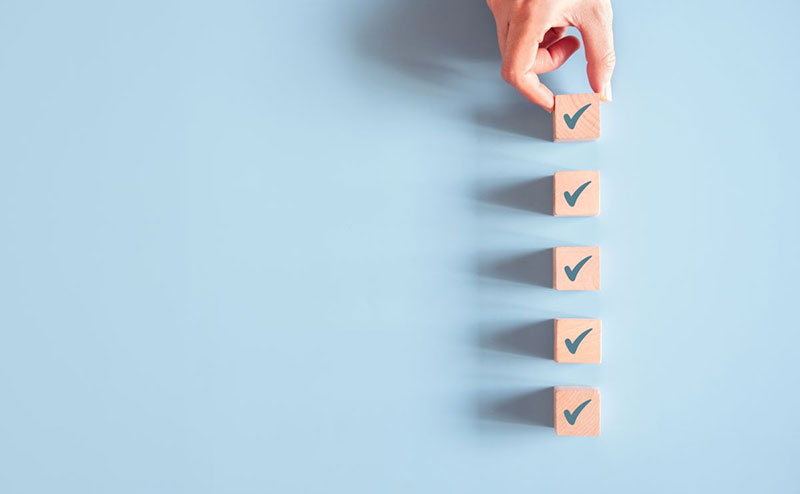
葬儀の日程を決める際は、さまざまな要素を考慮する必要があります。
ここでは、日程を決める際の主なポイントをご紹介します。
一般的なお葬式の日程
亡くなってから24時間以内は基本的には火葬を行うことが例外(特定の感染症などで亡くなった場合など)を除き出来ません。
これは「墓地、埋火葬に関する法律」の第3条で「埋葬又は火葬は、ほかの法令に別段の定があるものを除く他、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、これを行ってはならない。」と決められているためです。
これは「蘇生の可能性」があった時代の名残です。
一般的な葬儀の日程は、故人が亡くなった翌日に通夜、翌々日に葬儀・告別式を行います。
いつまでに葬儀をしなければならないという決まりはありませんが、ご遺体の状態を考慮するとなるべく早い方が望ましいです。
参列者の都合に合わせて決める
お通夜や葬儀の日程は、ご遺族や参列者の都合も考慮して調整します。
できるだけ多くの方に参列していただきたい場合は、曜日や時間帯に配慮することが大切です。
遠方からの参列者や海外から帰国する家族がいる場合は、葬儀の日程を親族の都合に合わせて調整する必要があります。
また、仕事の関係者など、参加しづらいタイミングが事前にわかる場合は、その日程は避けるようにします。
ただし、参列者が多い場合、すべての方に配慮するのは現実的ではないため、ご遺族や親族の方のスケジュールを優先して日程調整をするのが一般的です。
僧侶のスケジュールを確認する
仏教の葬儀では、僧侶にお経をあげていただきます。
菩提寺がある場合はできるだけ早く連絡をし、僧侶の都合を確認する必要があります。
菩提寺がない場合は、葬儀社に僧侶の手配をお願いすることもできます。
火葬場の空き状況を確認する
火葬場の空き状況を確認することも重要です。
特に都市部では、早々に予約で埋まってしまうことも多いため、早めの確認が大切です。
また、先ほども少し触れましたが、友引の日は多くの火葬場が定休日となっているため、その点も考慮する必要があります。
火葬場の手配は一般的に葬儀社が行いますので、担当者に確認しておくと安心です。
繁忙期には、火葬場の予約が取りにくく、混雑することがあります。
年末年始など時期によっては火葬場が休業していることもあるため、葬儀を行う場合は日程がずれ込む可能性があることも考えておきましょう。
年末年始の葬儀・火葬については、こちらもあわせてご覧ください。
地域の慣習に合わせる
葬儀の進行方法や六曜に関する慣習は地域によって異なります。
例えば、前火葬(葬儀前に火葬を行う)と後火葬(葬儀後に火葬を行う)の違いなど、地域によってどちらが一般的かは異なります。
また、六曜についても、地域によってどの程度重要視されるかが異なる場合があるため、確認しておくと安心です。
富士葬祭がある静岡県では、基本的には一般的な葬儀のしきたりと同じです。
しかし、一部地域では、昔ながらのしきたりや伝統が残っている地域もあります。
葬儀の日程の決め方や静岡県の葬儀のしきたりについては、こちらのコラムで解説しておりますので、あわせてご覧ください。
友引に葬儀を行うことは可能だが配慮すべき点もある
友引に葬儀を行うことは可能ですが、「友を引く」という考え方から避けられる傾向にあります。
友引の日は、火葬場が定休日となっていることも多いため、実際には友引の日に葬儀・告別式を行うのが難しい場合が多いでしょう。
一方で、お通夜については友引の日に行なっても問題ありません。
ただし、友引の翌日は火葬場が混雑しやすいため注意が必要です。
葬儀の日程は、亡くなった時間、参列者の都合、菩提寺や僧侶のスケジュール、火葬場の空き状況、地域の慣習などを考慮して決めていきます。
葬儀の日程調整などに不安や疑問があれば、富士葬祭がお答えします。
葬儀場の見学や事前相談も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。