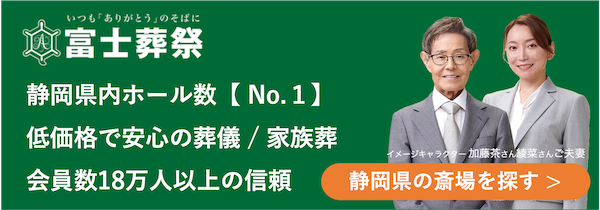BLOGS
葬儀・家族葬ブログ

葬儀の知識
お通夜とは何をする儀式かを解説。流れやマナーも確認
こんにちは。静岡の葬儀社 富士葬祭です。
訃報とは突然来るもの。
お通夜に参列することになった場合には、「お通夜では何するのだろう」「服装マナーは大丈夫かな」などと、不安を感じてしまう方もいるでしょう。
そこで今回のコラムでは、お通夜の基本情報について解説。
お通夜の意味や内容、儀式の流れ、参列時のマナーまで、詳しくご紹介します。

目次
お通夜とは
お通夜は、大切な人との最後の別れ、その始まりとなる儀式です。
葬儀・告別式の前夜に行われ、故人様の冥福を祈り、別れを惜しむ時間となります。
本来、お通夜は文字通り「夜を通して」行われる儀式でした。
遺族や近親者が故人様のそばでろうそくと線香の火を絶やすことなく見守る中、故人様があの世へ旅立つ準備を整える時間だったのです。
ろうそくや線香を絶やさないのは、故人様の魂があの世へ向かう道中を照らし、安らかな旅立ちを願う意味が込められています。
現代では、お通夜は、葬儀・告別式の前夜18~19時頃から、2~3時間程度で行われることが一般的です。
また、かつてはお通夜の前夜に、親族のみで「仮通夜」を行なってから、翌日にお通夜を行うこともありましたが、現代では仮通夜は省略されることが多いです。
さらに近年では、直葬や一日葬など、お通夜を行わない新しい葬儀形式も登場しています。
お通夜では何をする?流れを解説
お通夜の内容や全体的な流れをご紹介します。
はじめてお通夜に参列する場合でも、全体的な流れを知っておくことで安心して参列できるでしょう。
受付
遺族や親族は、準備のため開始時間の1時間前には会場に到着、一般参列者は15~30分前頃到着が目安です。
会場に到着したら、受付で香典を渡し、遺族へご挨拶をします。
着席
会場に案内されて着席します。
遺族や親族は前方、一般参列者は後方に着席するのが一般的です。
僧侶の読経
僧侶が入場し、読経を行います。
読経の時間は30分~1時間程度です。
焼香
読経の中、焼香を行います。
僧侶、喪主、遺族、親族、一般参列者の順番です。
焼香のやり方については「葬儀の焼香のやり方はどうする?作法やマナーを紹介」でも詳しくご紹介していますので、あわせてご覧ください。
喪主の挨拶・閉式
読経・焼香が終わると、僧侶が退場します。
喪主が挨拶を行い、お通夜が閉式となります。
通夜振る舞い
お通夜の閉式後には、「通夜振る舞い」という会食が設けられることがあります。
通夜振る舞いは、思い出話などをしながらともに食事をすることで故人様の供養となるとされています。
通夜振る舞いに呼ばれた場合は、ひと口でも箸をつけるのがマナーです。
なお、お通夜、通夜振る舞いが終わったあとには、故人様のご遺体のそばで遺族がろうそくや線香の火を絶やさず見守る「寝ずの番」をすることもあります。
お通夜のマナー

お通夜の主なマナーも確認しておきましょう。
参列者の範囲について
お通夜は、遺族や親族、親しい友人など、故人様の近親者が中心に参列します。
しかし、友人、知人、職場関係者などでも、昼間の葬儀・告別式に参列が難しい場合は、お通夜に参列するケースもあります。
服装について
お通夜へ参列する際の服装は、喪服が基本です。
ただし一般参列者は、喪服は訃報を予期していたようで不謹慎、急いで駆け付けたという意味を込めて平服でも良いとされています。
特に、仕事から直接参列する場合は、地味な色合いのスーツでも問題ありません。
なお、平服でもマナー違反にはなりませんが、近年では一般参列者も喪服を着用するケースが増えています。
香典について
不祝儀袋に香典を用意し、表書きには「御霊前」や「御香典」を記載します。
香典の表書きは宗派によって言葉が違うケースもあるため、故人様の宗派がわからないときには、共通で使用できる「御香典」としておくと良いでしょう。
金額は故人様との関係性や地域などにもよりますが、家族や親族では1万~5万円程度、友人や職場関係なら1万円前後が相場です。
香典の相場については、こちらのコラムもあわせてご覧ください。
遅刻について
「お通夜に遅刻しそう」という場合でも、30分~1時間程度なら遅刻して参列するケースもあります。
お通夜はそもそも「急いで駆け付ける」というものでもあるため、受付が開いていれば遅刻して参列して構いません。
ただし、2時間以上遅れてしまうなど迷惑をかけてしまいそうな場合は、お通夜への参列を控えることも検討しましょう。
なお、お通夜や葬儀のしきたりやマナーは、地域によって異なることがあります。
静岡地域のしきたりについては「静岡の通夜・葬儀のしきたりはある?昔ながらの作法を紹介」で詳しくご紹介していますので、ご覧ください。
お通夜で何をするのか理解してふさわしい振る舞いで参列を
お通夜とは、葬儀・告別式の前夜に近親者が集まり、故人様の冥福を祈り、別れを惜しむ儀式です。
かつては夜を通して行われる儀式でしたが、現代では、葬儀・告別式の前夜18~19時頃から2~3時間行われます。
お通夜は、受付後、着席→読経→焼香→喪主の挨拶という流れで進行。
閉式後に通夜振る舞いという会食の場を設けることもあります。
お通夜に参加するのは近親者が中心ですが、一般参列者が葬儀・告別式に出られない代わりにお通夜に参列するというケースも。
「急いで駆け付けた」という意味で、一般参列者は平服でもマナー違反とはなりませんが、最近は喪服を着用することも増えています。
参列する際は、服装や香典のマナーに気を配り、故人様を偲ぶ大切な儀式にふさわしい振る舞いを心がけましょう。
静岡県の葬儀は、富士葬祭におまかせください。
いざというときに慌てないためにも、葬儀場の見学や事前相談も承っております。