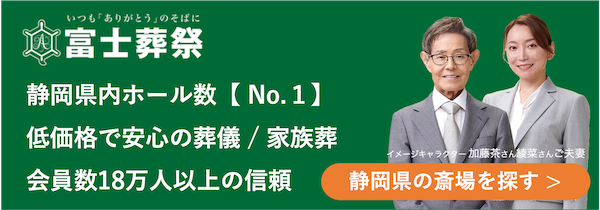BLOGS
葬儀・家族葬ブログ

葬儀の知識
葬儀の日程の決め方は?流れや注意点を紹介
こんにちは。静岡の葬儀社 富士葬祭です。
葬儀にはお通夜や告別式などさまざまな儀式がありますが、どのように日程を決めれば良いのでしょうか。
日程を決める際は、注意点に気をつけながら日程を決める必要があります。
そこで今回は、葬儀の日程の決め方についてお話しします。
葬儀の種類別の日程などもご紹介しますので、参考にしてください。

目次
葬儀の日程の決め方とは?
葬儀の日程は、故人様が安置された後に葬儀社と打ち合わせを行い、その場で決定するのが一般的です。
ただし、亡くなったのが深夜などの場合は、後日改めて調整を行うこともあります。
葬儀の日程は、喪主を中心に決めていくのが一般的です。
日程を決める順番としては、葬儀・告別式と火葬を同じ日に行うため、最初にその日時を決定します。
葬儀の開始時間は、通常午前中や午後の早い時間帯になることが多いです。
また、葬儀後には「初七日法要」や「精進落とし」の会食が行われることもあるため、その日程もあわせて決定します。
葬儀日程が決まると、次は通夜の日程を決めます。
通夜は一般的には葬儀の前日に行われ、参列者が仕事や学校を終えてから参加しやすいよう、18~19時開始が多いです。
葬儀の日程を決める際の確認ポイント
葬儀の日程を決める際、最初に確認が必要なのは、菩提寺(ぼだいじ)や僧侶のスケジュール、そして参列する親族のご都合です。
菩提寺がある場合は、葬儀の読経を菩提寺の僧侶に依頼するのが一般的です。
故人様が亡くなったらすぐにお寺に連絡をし、読経をお願いできる日程を調整しましょう。
特にお盆やお彼岸の時期は寺社が混み合うため、早めにスケジュールを確認して調整することが重要です。
また、遠方から参列する親族や海外から帰国する家族がいる場合は、葬儀の日程を親族の都合に合わせて調整する必要があります。
葬儀社に事前に伝えた上で、スケジュール調整を進めていくと安心です。
菩提寺や親族のご都合に合わせて、火葬場や葬儀場の空き状況を確認します。
特に都市部では、早々に予約で埋まってしまうことも多いため、早めの確認が大切です。
一般的な葬儀の日程の決め方をケースごとに紹介

一般的な葬儀の日程について、「一般葬・家族葬」「一日葬」「直葬」のそれぞれの日程の例をご紹介します。
一般葬・家族葬の日程
一般的な葬儀である一般葬や、親族など親しい方々だけで行う家族葬は、3日間もしくは4日間の日程で行われます。
【3日間の日程】
- 1日目:ご逝去、葬儀社の手配・打ち合わせ、ご遺体の搬送・安置
- 2日目:通夜、通夜振る舞い
- 3日目:葬儀・告別式、出棺、火葬
【4日間の日程】
- 1日目:ご逝去、葬儀社の手配・打ち合わせ、ご遺体の搬送・安置
- 2日目:仮通夜(枕経)
- 3日目:通夜、通夜振る舞い
- 4日目:葬儀・告別式、出棺、火葬
深夜や早朝にお亡くなりになった場合、通夜を当日に行うこともありますが、準備に時間が足りない可能性があるため、2日目に通夜を行うのが一般的です。
また、火葬場や参列者のスケジュール、友引などの諸事情により、通夜の前に仮通夜を行なって、葬儀を4日間かけて行うケースもあります。
一日葬の日程
一日葬とは、葬儀を1日で全て完了させる形式の葬儀です。
一日葬では通夜を省略し、葬儀・告別式・火葬を1日に集約して行います。
- 1日目:ご逝去、葬儀社の手配・打ち合わせ、ご遺体の搬送・安置
- 2日目:葬儀・告別式、出棺、火葬
直葬の日程
直葬とは、通夜や告別式を省略し、火葬だけを行う葬儀です。
最もシンプルな葬儀といえるでしょう。
- 1日目:ご逝去、葬儀社の手配・打ち合わせ、ご遺体の搬送・安置
- 2日目:納棺、火葬
葬儀の日程の決め方で注意するポイント
葬儀の日程を決定する際は、次のようなポイントに注意しましょう。
友引に配慮する
「友引」は、六曜における一つの日で、「友を引く」という意味から、縁起が悪い日とされています。
特に葬儀を避ける習わしがあり、火葬場が休業していることが多い日です。
これにより、友引の日には葬儀・告別式を避けることが一般的とされていますが、通夜は問題なく行われることも多いです。
火葬ができない時間がある
日本では、死亡から24時間以内に火葬を行うことは、例外(特定の感染症などで亡くなった場合など)をのぞき、法律で禁止されています。
そのため、直葬の場合などは特に注意して日程を決める必要があります。
地域の慣習を確認する
葬儀の進行方法や六曜に関する慣習は地域によって異なります。
例えば、前火葬(葬儀前に火葬を行う)と後火葬(葬儀後に火葬を行う)の違いなど、地域によってどちらが一般的かは異なります。
また、六曜についても、地域によっては「仏滅」や「先負」の日を避ける習慣が強い場合があるため、確認しておくと安心です。
富士葬祭がある静岡県では、基本的には一般的な葬儀のしきたりと変わりありませんが、昔ながらのしきたりや伝統が残っている地域もあります。
こちらのコラムで解説しておりますので、あわせてご覧ください。
時期に注意する
年末年始やお盆などの繁忙期には、火葬場の予約が取りにくく、混雑することがあります。
また、年始の三が日は火葬場が休業していることが多いため、年末年始に葬儀を行う場合は、日程がずれ込む可能性が高くなります。
詳しくは下記コラムでご紹介していますので、あわせてご覧ください。
葬儀日程の決め方に不安があれば葬儀社へ相談を
葬儀の日程は、故人様が安置された後に葬儀社と打ち合わせを行い決定します。
亡くなった時間帯によっては、日程調整を後日に行う場合もあります。
日程の決定は、喪主を中心に進めていくのが一般的です。
基本的には、葬儀・告別式と火葬を同日に設定します。
通夜は参列者が参加しやすいよう、18~19時開始が多いです。
日程調整では、菩提寺や僧侶のスケジュール、参列する親族のご都合なども考慮し、火葬場や葬儀場の空き状況の確認を進めていきます。
一般葬や家族葬は通常3日間から4日間の日程で行い、一日葬は1日で全てを完了させます。
直葬は火葬のみ行い、通夜や告別式を省略します。
友引や、火葬が24時間以内はできないこと、地域の慣習、繁忙期の火葬場予約などに注意する必要がありますが、不安があれば葬儀社に相談しながら進めると安心です。
静岡県の葬儀は、富士葬祭におまかせください。
いざというときに慌てないためにも、葬儀場の見学や事前相談も承っております。