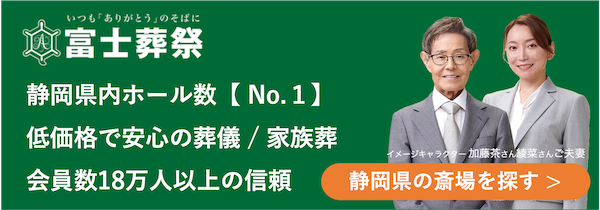BLOGS
葬儀・家族葬ブログ

葬儀の知識
葬儀の宗教による違いとは?種類ごとの特徴とマナーを解説
こんにちは。静岡の葬儀社 富士葬祭です。
日本では仏教式の葬儀が一般的ですが、そのほかにも神道やキリスト教、無宗教など、さまざまな宗教・宗派による葬儀が執り行われています。
葬儀を執り行う際、または葬儀に参列する際に、宗教ごとのマナーや流れがわからないと不安に感じることもあるでしょう。
そこで今回のコラムでは、日本で行われる主な宗教の葬儀の特徴や違い、それぞれのマナーについて解説します。
葬儀の宗教による違いを知ることで、大切な方を見送る際の不安を少しでも解消できれば幸いです。

葬儀の宗教の種類
日本で行われている葬儀の宗教は、主に以下の4つに分類されます。
- 仏教式:日本の葬儀の約9割を占める最も一般的な形式
- 神道式(神葬祭): 日本古来の民族宗教である神道の葬儀
- キリスト教式:聖書の教えに基づき、神への祈りと儀式を行う葬儀
- 無宗教式:宗教や慣習にとらわれない自由な形式の葬儀
日本における宗教の信仰割合はさまざまですが、葬儀に関しては約9割が仏教式で行われているといわれます。
これは、日本人の多くが仏教の葬送儀礼を文化として受け継いでいるためです。
しかし近年では、個人の価値観の多様化に伴い、宗教的な儀式を簡略化したり、無宗教の葬儀を選択したりするケースも増加しています。
また、葬儀は宗教による違いのほか、家族葬や一日葬など、さまざまな種類の形式があります。
「葬儀の種類をご紹介!メリットやデメリットも」のコラムで詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
宗教による葬儀の違い

各宗教の葬儀の特徴や違いについて詳しく見ていきましょう。
葬儀に参列する際のマナーや注意点も紹介します。
仏教式葬儀の特徴とマナー
仏教式葬儀は日本で最もなじみ深く、一般的な葬儀形式です。
仏教の教えでは、人は死後に成仏して仏になると考えられており、葬儀は故人様の冥福を祈り、あの世への旅立ちを見送る儀式として執り行われます。
基本的な流れは、通夜と告別式の2日間にわたって行われることが多いですが、最近では一日葬や直葬という形で簡略化されることもあります。
仏教式葬儀の主な特徴は以下の通りです。
- 僧侶(導師)による読経
- 参列者による焼香
- 数珠の使用
- 戒名の授与
参列者は黒の喪服を着用し、数珠を持参します。
焼香の方法は宗派によって異なる部分もありますが、一般的には香を少量つまみ、額の高さまで持ち上げてから香炉に落とします。
また、数珠も正式には宗派によって形状や扱いが異なりますが、一般参列者の場合は略式数珠の持参で問題ありません。
葬儀での焼香や数珠については、こちらで詳しくご紹介しています。
仏教の主な宗派と葬儀の違い
仏教には多様な宗派があり、それぞれに葬儀の考え方や作法が異なります。
主な宗派の特徴を以下に紹介します。
【浄土真宗】
浄土真宗では、人は死後すぐに仏の世界に入る「即身成仏」という考え方があります。
そのため、「お悔やみ申し上げます」「ご冥福をお祈りします」などの表現は避けるべきとされています。
同様に香典の表書きには「御霊前」ではなく、「御仏前」や「御香典」と記すのが適切です。
【浄土宗】
浄土宗では、「南無阿弥陀仏」を唱え、阿弥陀仏の力を借りて極楽浄土に行くという考えのもとに葬儀が行われます。
僧侶と参列者が一緒に念仏を唱える「念仏一会」が特徴です。
【日蓮宗】
日蓮宗では、葬儀を亡くなった方の「最後の修行の機会」と捉えています。
この儀式を通じて、故人様を「霊山浄土」と呼ばれる世界へ導くことを目指します。
【禅宗(臨済宗/曹洞宗)】
禅宗の葬儀は、故人様に戒律を授けて正式な仏弟子とする「授戒」と、仏の世界へ導く「引導」という二つの儀式を中心に行われます。
【真言宗】
真言宗では、葬儀を「大日如来のもとへ帰る儀式」と考えています。
この世での肉体のままで仏になる「即身成仏」の思想に基づき、葬儀の中で故人様に特別な印を結び、真言(マントラ)を唱えることで、故人様が仏と一体になることを目指します。
神葬祭(神式)の特徴とマナー
神葬祭は、日本の民族宗教である神道に基づく葬儀形式です。
神道では「故人の魂を家の守り神として祀る」ための儀式として葬儀が行われます。
葬儀を通して、故人様は祖先神となり家族を守る存在となります。
死は「穢れ」とみなされるため、神聖な場所である神社ではなく、自宅や葬儀場などで葬儀が行われます。
神葬祭の主な特徴は以下の通りです。
- 神職による祝詞の奏上
- 焼香ではなく「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」を行う
- 香典ではなく「御玉串料」を渡す
- 数珠は使用しない
神葬祭の流れは1日目に「通夜祭」「遷霊祭」、2日目に「葬場祭」「火葬祭」などが行われます。
参列者は仏教式と同様に黒の喪服を着用しますが、数珠は持参しません。
また、玉串奉奠では、榊の枝に紙垂(しで)をつけた玉串を両手で捧げ、「二拝二拍手一拝」の作法でお参りします。
神葬祭では仏教用語を使わないため、「成仏」「冥福」「供養」などの言葉は避け、「御霊の平安をお祈りいたします」などの表現を用いるようにしましょう。
キリスト教式葬儀の特徴とマナー
キリスト教では、死は「永遠の命の始まり」と考えられています。
葬儀は故人様が神のもとに召されることを祝福する儀式であり、故人様にとっては地上での最後の祈りの場、遺族にとっては愛する人を神の御手に委ねる祈りの場とされています。
キリスト教式葬儀の主な特徴は以下の通りです。
- 教会で行われることが多い
- 神父または牧師による司式
- 聖書朗読、賛美歌の斉唱
- 焼香ではなく「献花」を行う
- 香典ではなく「お花料」を渡す
参列者は黒の喪服を着用しますが、数珠は必要ありません。
また、キリスト教では死を祝福する儀式と考えるため、お悔やみの言葉は不要です。
代わりに「安らかな眠りをお祈りいたします」など、故人様の安寧を祈る言葉をかけると良いでしょう。
香典にあたる「お花料」は、ユリの花や十字架がデザインされた特別な袋や白い封筒に入れて渡します。
カトリックとプロテスタントの違い
キリスト教式葬儀は、カトリックとプロテスタントの2つの宗派によって内容が異なります。
【カトリック式】
カトリックの葬儀では、故人様の罪を赦していただくよう神に祈り、キリストの再臨と死者の復活を願います。
葬儀は故人様が所属していた教会で行われ、司式者は「神父(司祭)」と呼ばれます。
一般的に葬儀と告別式は別々に行われ、通夜の習慣はもともとありませんでしたが、最近では日本の慣習を取り入れて「通夜祭」が行われることも増えています。
【プロテスタント式】
プロテスタントの葬儀は、カトリックよりも自由度が高く、柔軟性があります。
故人様は神のもとで安らかになるという考えのもと、神に感謝し、遺族を慰める儀式となります。
葬儀と告別式は通常一緒に行われ、司式者は「牧師」と呼ばれます。
また、前夜に「前夜祭」が行われるのが一般的です。
無宗教葬(自由葬)の特徴とマナー
無宗教葬は、宗教的な儀式や慣習に縛られず、故人様や遺族の希望に沿った自由な形で執り行われる葬儀です。
故人様との「お別れの会」や「偲ぶ会」としての要素が強く、故人様を偲ぶ心が重視されています。
無宗教葬の主な特徴は以下の通りです。
- 僧侶などの宗教人による読経などは原則なし
- 流れや儀礼などの決まり事が基本的になく、希望に応じて組み立てる
- さまざまな形態の葬儀が選べる
無宗教葬には、故人様の好みだった音楽を生演奏する「音楽葬」や、食事をしながら故人様を偲ぶ「レストラン葬」、キャンドルの光で故人様を悼む「キャンドル葬」など形式はさまざまです。
無宗教葬について詳しく知りたい方は、「自由葬とは?特徴やメリット・デメリットと注意点も紹介」もあわせてご覧ください。
葬儀の宗教の違いを知って適切に対応しよう
葬儀の宗教や宗派による違いを知ることで、急な参列時でも焦らずに対応できます。
日本では約9割が仏教式の葬儀ですが、神道やキリスト教、無宗教の葬儀もあり、それぞれに特徴や作法が異なるため、事前に確認しておくと安心です。
特に言葉遣いは宗教によって適切な表現が異なりますので、注意が必要です。
また、仏教でも宗派によって葬儀に対する考え方や焼香の方法などが違いますので、わからない場合は会場のスタッフなどに確認してみてくださいね。
静岡県の葬儀は、富士葬祭におまかせください。
いざというときに慌てないためにも、葬儀場の見学や事前相談も承っております。