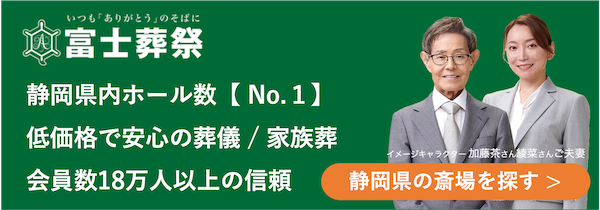BLOGS
葬儀・家族葬ブログ

葬儀の知識
葬儀の案内状とは?種類や送るタイミング、注意点をわかりやすく解説
こんにちは。静岡の葬儀社 富士葬祭です。
大切な方との突然の別れに直面したとき、葬儀に向けた準備と同時に多くの方への連絡も行わなければなりません。
心の整理がつかない中での案内状作成は想像以上に大変なものです。
「どのタイミングで連絡すべきか」「どのような内容を書けばよいのか」「案内状の作成時に注意点はあるか」などと戸惑われる方も多いのではないでしょうか。
今回は、葬儀に関する案内状の種類や適切な作成方法、送るべきタイミングについてわかりやすく解説します。
実際に使える例文も用意しましたので、ぜひご活用ください。
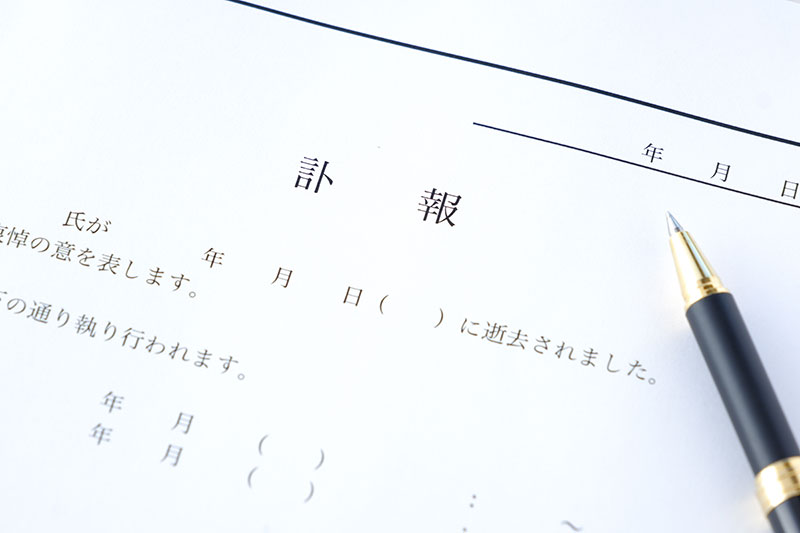
目次
葬儀の案内状とは?種類も確認
葬儀の案内状は、故人様が亡くなったことや葬儀の情報を関係者に伝えるものです。
場面や目的によって種類が異なり、それぞれ送るタイミングや相手も変わってきます。
葬儀前に送る案内状
葬儀が行われる前に送る案内状は、ご逝去の知らせと葬儀への参列案内を兼ねています。
主に記載すべき内容は次のようなものです。
- 故人様のお名前と年齢
- ご逝去された日時
- 通夜・葬儀告別式の日程と場所
- 喪主の名前と連絡先
- 葬儀の形式(仏式・神式など)
この案内状は、親族や故人様と深い関わりのあった方々へ向けて送られます。
葬儀の連絡を兼ねる場合は、通夜や葬儀に間に合うようすぐに連絡します。
FAXやメールなどのほか、電話で内容を伝えるなど、即時性の高い手段が選ばれることが一般的です。
葬儀後に送る案内状
葬儀終了後に送付する案内状は、主に2つの目的があります。
葬儀報告の案内状
家族葬など身内で葬儀を執り行なった場合や、遠方にお住まいの方など参列できなかった方に、葬儀が無事に終了したことを報告します。
葬儀から1週間~1カ月以内を目安に郵送するのが一般的で、年末に近い時期の場合は、喪中はがきと兼ねることもあります。
お礼状(会葬礼状)
葬儀に参列された方や香典・弔電をいただいた方へのお礼の気持ちを伝えます。
こちらは葬儀当日に会場で直接お渡しすることが多いです。
法要の案内状
四十九日法要や一周忌などの法要を行う際に、参列をお願いしたい方へ送る案内状です。
法要の日程や場所、会食の予定などを記載します。
出欠の返事をもらう時間的余裕も含め、法要の1カ月前頃までに送付します。
出欠確認のために返信用はがきを同封するのが一般的です。
葬儀の案内状を例文でチェック

それぞれの案内状について、実際の書き方を例文でご紹介します。
状況に応じてアレンジして活用ください。
<葬儀前の案内状(訃報)の例文>
父 〇〇〇〇につきまして 令和〇年〇月〇日に逝去いたしましたので 謹んでご通知申し上げます
生前中のご厚情に深く感謝申し上げます
つきましては下記のとおり葬儀を執り行います
通夜式 令和〇年〇月〇日 午後6時より
葬儀告別式 令和〇年〇月〇日 午前11時より
会場 富士セレモニーホール(住所 静岡県〇〇市… 電話 000-000-0000)
儀式 仏式(〇〇宗)
喪主 △△△△(長男)
令和〇年〇月〇日
△△△△
<葬儀後の報告をする案内状の例文>
母 〇〇〇〇儀 かねてより療養中でございましたが
去る〇月〇日に75歳にて逝去いたしました
生前に賜りましたご厚誼に心より感謝申し上げます
なお 葬儀につきましては母の遺志に従い 近親者のみにて執り行いました
事後のご報告となり恐縮ではございますが 謹んでご通知申し上げます
静岡県〇〇市〇〇町…
喪主 △△△△
並びに親族一同
<葬儀参列へのお礼の案内状の例文>
父 〇〇〇〇 儀 葬儀に際しましてはご多用中にもかかわらずご会葬いただき 誠にありがとうございました
心より御礼申し上げます
また故人が生前賜りましたご懇情に対しましても茲に併せて厚く御礼申し上げます
早速拝趨の上ご挨拶申し上げるのが本意でありますが略式ながら書中を以ってお礼申し上げます
令和〇年 〇月〇日 通夜
〇月〇日 葬儀告別式
静岡県〇〇市〇〇町…
喪主△△△△
並びに家族一同
<法要に関する案内状の例文>
謹啓
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます
さて このたび故〇〇〇〇の四十九日法要を下記のとおり執り行います
ご多用中誠に恐縮ですが ご参列いただけますようご案内申し上げます
謹白
記
日時 令和〇年〇月〇日 午前11時より
場所 〇〇寺(静岡県〇〇市〇〇町… 電話 000-000-0000)
法要後 〇〇にて会食を予定しております
令和〇年〇月〇日
静岡県〇〇市〇〇町…
施主 △△△△
喪主は葬儀において多くの役割を担いますが、案内状の作成・送付もその一つです。
喪主の役割について詳しく知りたい方は、「葬儀の喪主がやることとは?準備から葬儀後までの流れと注意点を解説」をご参照ください。
葬儀の案内状を作成する際の注意点
心を込めた丁寧な案内状を作るためにも、葬儀の案内状作成時のポイントやマナーを確認しておきましょう。
句読点は使用しない
葬儀関連の案内状では、句読点(「。」や「、」)を使いません。
これは文章の区切りが「終わり」を象徴するとされているためです。
文章を読みやすくするには、句読点の代わりにスペースを入れるか、適宜改行を入れて対応します。
忌み言葉を使わない
不幸や不吉を連想させる「忌み言葉」は避けるべきです。
特に以下のような表現には注意が必要です。
- 死や苦に通じる言葉(「死亡」「四」「苦しい」など)
- 不幸を想起させる言葉(「迷う」「沈む」「落ちる」など)
- 繰り返しを表す言葉(「たびたび」「重ねて」「また」など)
例えば「また何かございましたら」という表現は、「また不幸があったら」と取られかねないため避け、「何かございましたら」とシンプルにするのが無難です。
日付は元号表記を使用する
案内状内の日付は、西暦ではなく元号(令和など)で表記するのが基本的なマナーです。
また、葬儀関連の案内状や表書きでは、数字は漢数字を使うことが多いですが、最近ではアラビア数字も使われています。
香典・供花を辞退する場合は明示する
家族葬や香典・供花を辞退する場合は、その旨を案内状にはっきりと記載しましょう。
「故人の遺志により香典・供物・弔電は固くご辞退申し上げます」といった文言を加えることで、参列者の不安や迷いを取り除けます。
葬儀の案内状は種類ごとのポイントを押さえて丁寧に作成を
葬儀に関する案内状には、訃報を伝えるものから葬儀後の報告、お礼状、法要の案内などの種類があります。
それぞれ目的や送るタイミングが異なるため、状況に応じて適切なものを選ぶことが大切です。
案内状作成の際は、句読点を使わない、忌み言葉を避ける、元号で日付を記すなどの基本的なマナーを守り、故人様との関係性に配慮した文面を心がけましょう。
また家族葬や香典を辞退する場合は、その意向をはっきりと伝えることで参列者の戸惑いを防ぎます。
葬儀は故人様への最後のお別れの場であり、案内状はその大切な第一歩です。
丁寧な案内状を通じて、故人様を偲ぶ気持ちと関係者への感謝の気持ちを表現しましょう。
静岡県の葬儀は、富士葬祭におまかせください。
いざというときに慌てないためにも、葬儀場の見学や事前相談も承っております。