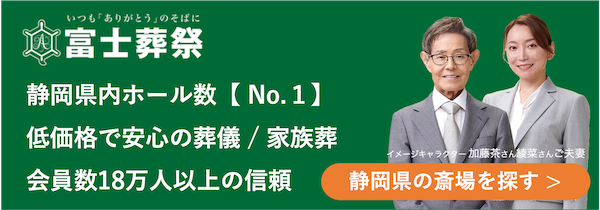BLOGS
葬儀・家族葬ブログ

葬儀の知識
葬式での喪主挨拶。タイミングや内容、注意点を確認
こんにちは。静岡の葬儀社 富士葬祭です。
葬式における喪主とは、故人様の葬式の際に、儀式の運営や遺族を代表して手続きを行う人のことを指します。
喪主の大切な務めの一つが、喪主挨拶です。
今回は、葬式での喪主挨拶についてお話しします。
挨拶をするタイミングや挨拶の例文、気を付けるべきことなどもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

目次
葬式で喪主が挨拶するタイミングは?
まずは葬式の流れを見ていきましょう。
葬式は、一般的に次のような流れで行われます。
- 逝去・搬送・安置
- 葬儀社と打ち合わせ
- 納棺
- 通夜
- 葬儀・告別式
- 出棺・火葬
- 精進落とし
この中で、喪主が挨拶を行うタイミングは、「通夜」「葬儀・告別式」「精進落とし」です。
なお、家族や親族、親しい友人のみで行う家族葬の場合も、一般的には喪主の挨拶を行うことが多いです。
ただし、数人の家族のみで行う場合は、挨拶は省いても差し支えありません。
葬式の流れについては下記コラムで詳しくご紹介していますので、あわせてご覧ください。
初めて喪主になられる方へ。葬儀の流れや押さえるポイントを解説。
葬式での喪主の挨拶を例文で確認
葬式で喪主が行う挨拶について、「通夜」「葬儀・告別式」「精進落とし」の3つのタイミングに分け、それぞれの挨拶の例文をご紹介します。
喪主挨拶を行う際は、ぜひ参考にしてください。
【通夜】の喪主挨拶の例文
通夜では、僧侶が退席後の通夜終了時に喪主が挨拶を行います。
弔問者に参列してくれたことへのお礼をし、通夜ぶるまいがある場合はその旨を案内します。
例文
本日はお忙しい中、父○○の通夜式にご参列いただき、心より感謝申し上げます。
故人もさぞかし喜んでいることと存じます。
生前に賜りましたご厚情に対し、改めてお礼を申し上げます。
なお、明日の葬儀・告別式は△△時より本会場で執り行います。
本日は誠にありがとうございました。
(通夜ぶるまいがある場合)
なお、ささやかではございますが、別室にてお食事をご用意しております。
ご都合のよろしい方は、ぜひお越しいただき、故人の生前の思い出などお聞かせいただければ幸いです。
【葬儀・告別式】の喪主挨拶の例文
葬儀・告別式でも、僧侶の退席後に挨拶をします。
参列のお礼や生前の厚意への感謝の気持ちを伝えるほか、故人様の生前のエピソードやお人柄、最後に遺族への力添えをお願いする旨を入れることが多いです。
なお、出棺の時にお礼の挨拶をする場合もあります。
例文
皆様、本日はお忙しい中、父○○の葬儀、並びに告別式にご参列いただきありがとうございました。
父は映画鑑賞が大好きで、家で映画を観ることはもちろん、私が子どものときにもよく映画館に連れて行ってもらいました。
学生時代に友人や勉強のことで悩んでふさぎがちになっていたとき、「映画でも観るか」と連れ出してくれたことは今でもよく覚えています。
多くを語らない父でしたが、いつも私たち家族を見守り、支えてくれていました。
これからも、私たちのそばで見守っていてくれていることと思います。
亡き父になりかわりまして、生前に受け賜りましたご厚誼に心からお礼申し上げます。
今後も変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
本日は誠にありがとうございました。
【精進落とし】の喪主挨拶の例文
精進落としとは、火葬や初七日法要の後に、お世話になった方々に感謝の気持ちを込めてふるまう食事です。
精進落としでは、会食の始まりに簡単な挨拶をして、葬式を無事に終えられたことに対して感謝の意を述べましょう。
例文
本日はご多忙中のところを亡き○○のために、いろいろとお心遣いいただき、ありがとうございました。
おかげさまをもちまして、本日滞りなく葬儀・告別式をすませることができました。
あらためてお礼を申し上げます。
ささやかではございますが、精進落としの膳を用意しましたので、ごゆっくりお召し上がりいただきたいと思います。
本当にありがとうございました。
葬式での喪主挨拶で気を付けるべきこと

葬式の喪主挨拶で気を付けるべきポイントやマナーを見ていきましょう。
挨拶の長さと内容
喪主の挨拶は、一般的に1~3分程度で簡潔にまとめることが大切です。
長すぎると参列者が疲れてしまいますし、短すぎると不十分に感じられる可能性があります。
挨拶文は、参列者へのお礼や感謝の意を必ず入れます。
過度に個性を出す必要はありませんが、故人様のお人柄が感じられるエピソードを入れると良いでしょう。
なお、挨拶をうまくまとめる自信がない場合は、メモを見ながら話しても問題ありません。
忌み言葉・重ね言葉
喪主挨拶をはじめ、葬式では忌み言葉や重ね言葉を避ける必要があります。
これらの言葉は不幸が重なることを連想させるため、葬儀の場で使うのは良くないとされています。
具体的には、以下の言葉は使わないようにしましょう。
- 重ね言葉:たびたび、しばしば、再三、重々、何度も など
- 忌み言葉:消える、浮かばれない、急死、迷う、死ぬなど
話すスピード
緊張しやすい葬式の場では、ゆっくりと話すことが大切です。
早口で話すと、参列者が理解しづらくなります。
簡潔で分かりやすい表現を使い、気持ちが伝わるように心がけましょう。
宗教や形式に応じた配慮
葬儀の宗教や形式に合わせた言葉遣いも重要です。
仏教、神道、キリスト教など宗教ごとに異なる礼儀や挨拶の仕方がありますので、不安な場合は葬儀社に確認しましょう。
葬式での喪主挨拶のタイミングは主に3回
葬式で喪主が挨拶を行うタイミングは、通夜、葬儀・告別式、精進落としの3回です。
通夜では弔問者に感謝の気持ちを伝え、葬儀・告別式では生前に対する感謝や故人様のエピソードを語ります。
精進落としでは、葬儀を無事に終えたことへのお礼を述べます。
挨拶は1~3分程度、長すぎず短すぎずがポイントです。
忌み言葉や重ね言葉を避け、ゆっくりと丁寧に話すと、参列の方々への感謝の気持ちや故人様を偲ぶ気持ちが伝わりやすいです。
宗教や形式に応じた挨拶もあるので、心配な場合は葬儀社に確認をするのがおすすめです。
静岡県の葬儀は、富士葬祭におまかせください。
いざというときに慌てないためにも、葬儀場の見学や事前相談も承っております。