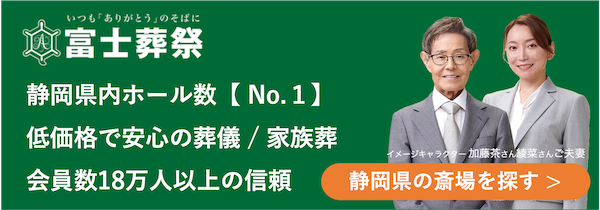BLOGS
葬儀・家族葬ブログ

葬儀の知識
喪主は誰がやる?決め方から役割までわかりやすく解説
こんにちは。静岡の葬儀社 富士葬祭です。
身近な方が亡くなった際、「喪主は誰が務めるべきなのか」「どのようなことをするのか」と戸惑う方も少なくありません。
喪主の決め方や役割を理解しておくことで、いざというときにもスムーズに葬儀を進めることができます。
今回のコラムでは、喪主の基本的な意味から決め方の優先順位、具体的な役割、そして知っておきたいマナーまで詳しくご紹介します。

目次
喪主とは
喪主とは、葬儀や法要を執り行う責任者のことを指します。
故人様に代わって弔問を受ける「遺族の代表者」としての役割を担い、葬儀全体を主催し、周囲に気を配りながら式を進めていく立場です。
葬儀当日だけでなく、その後の年忌法要なども主催し、参列者への挨拶や感謝を述べる場面も多くあります。
故人様がお世話になった方々に対し、ご遺族を代表して丁寧に対応することが求められる重要な役割です。
喪主と施主の違い
喪主と混同されやすいのが「施主」という立場です。
- 喪主:葬儀全体を執り仕切る責任者
- 施主:葬儀費用を負担し、金銭面で責任を持つ人
具体的には、葬儀の進行や打ち合わせは喪主が中心となり、費用の契約や支払いは施主が担います。
近年は喪主と施主を同一人物が務めるケースが多いですが、喪主が高齢の場合や経済的な事情がある場合には、別の親族が施主を担当することもあります。
喪主は誰がやる?決め方と優先順位
喪主を誰が務めるかについて法的な決まりはありませんが、一般的には一定の優先順位があります。
ここでは、優先順位順にご紹介します。
基本的には故人様との関係が深く、葬儀後も継続して供養できる人が選ばれます。
①配偶者
最も多いのは、故人様の配偶者が喪主を務めるケースです。
夫婦のどちらかが亡くなった場合、残された配偶者が喪主を務めるのが一般的です。
ただし、高齢や体調面の不安がある場合、あるいはすでに他界している場合には、ほかの親族が引き継ぎます。
②家族・親族
故人様に配偶者がいない場合や、配偶者が喪主を務めることが難しい場合は、家族や親族が喪主を務めます。
一般的には長男、次男といった直系の男性が優先され、その後に長女や次女といった直系の女性が続きます。
子供がいない場合は、両親、兄弟姉妹、さらに叔父や叔母といった近親者の中から選ばれます。
ただし、血縁関係だけでなく、故人様との生活状況や同居の有無、地理的条件なども考慮することが大切です。
③友人・知人
故人様に配偶者や親族がいない場合は、親しい友人や知人が喪主を務めることもあります。
長年の友人や日常的に支えていた近所の方が選ばれる場合もあります。
なお、喪主は一人に限らず、兄弟姉妹など複数人で務めることも可能です。
複数人で喪主を務めることで、一人ひとりの負担を軽減し、協力しながら葬儀を進めることができます。
喪主の役割

喪主は葬儀の準備から当日の進行、葬儀後の対応まで幅広い役割を担います。
役所での死亡手続き
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外の場合は3カ月以内)に提出しなければなりません。
死亡地、本籍地、または届出人の居住地の役所に届け出ます。
この手続きを済ませないと火葬や埋葬ができないため、迅速に行う必要があります。
葬儀社によっては代行サービスもあるため、依頼時に確認すると安心です。
葬儀の準備
宗教・宗派に沿った形式を確認し、葬儀社と規模や予算、会場、参列者数などを打ち合わせます。
短期間で多くの決定が必要になるため、家族や親族と協力して進めることが大切です。
葬儀の日程や費用の決定
僧侶や火葬場の予定を調整し、日程を確定します。
お盆やお彼岸などの繁忙期には予約が取りにくいこともあるため、早めの連絡と調整が必要です。
費用は施主と相談し、葬儀社と詳細を確認しながら適切に設定します。
寺院との連絡
菩提寺がある場合は僧侶へ訃報を伝え、読経を依頼します。
日程調整のほか、葬儀当日には僧侶を出迎えて挨拶し、控室へ案内するのも喪主の役割です。
代表の挨拶
喪主の重要な役割の一つが、遺族を代表しての挨拶です。
通夜・告別式の開始や終了、出棺前、精進落としなどのさまざまな場面で挨拶を行います。
自己紹介、参列者への感謝、故人様との思い出、今後のご縁へのお願いを含め、3分程度にまとめて話すのが望ましいでしょう。
香典返し
いただいた香典に対するお返しとして、香典返しを準備します。
一般的には香典の3分の1〜半額程度の品物(食品や日用品など)を選びます。
従来は忌明け後に渡すのが主流でしたが、最近は当日にお返しする「即日返し」も増えています。
喪主の役割や葬儀での流れについては以下のコラムでも詳しくご紹介しています。
あわせてぜひご覧ください。
葬儀の喪主がやることとは?準備から葬儀後までの流れと注意点を解説
喪主のマナーも確認
喪主は遺族の代表として、立ち居振る舞いに配慮する必要があります。
服装
喪主は参列者よりも格式の高い服装を心がけます。
- 男性:正喪服は紋付き羽織袴やモーニング、準喪服はブラックスーツ
- 女性:正喪服は黒の紋付き着物やブラックフォーマル、準喪服は黒のアンサンブルやワンピース
現在では準喪服を着用する喪主も増えています。
露出は控えめにし、派手な色や光沢のある素材は避けることが重要です。
髪型
清潔感が大切です。
男性は前髪が目にかからないよう整え、整髪料は無香料を選びます。
女性はお辞儀や焼香の際に髪が顔にかからないよう耳より下でまとめ、ヘアアクセサリーをつける場合は黒色のシンプルなものを用います。
アクセサリー
基本的にアクセサリーは控えますが、結婚指輪、時計、真珠のネックレス(一重のみ)は着用しても問題ありません。
真珠は「涙の象徴」ともいわれ、弔意を表す品としてふさわしいとされています。
参列者や僧侶への対応
喪主はご遺族の代表として、参列者や僧侶に対して丁寧で落ち着いた対応を心がけることが大切です。
弔問を受ける際は「ありがとうございます。故人もきっと喜んでいると思います」といった心のこもった言葉で応対し、参列者一人ひとりに感謝の気持ちを示しましょう。
喪主が初めてでご不安がある方は「初めて喪主になられる方へ。葬儀の流れや押さえるポイントを解説。」のコラムもご参考ください。
喪主を誰がやるか適切に決めて故人様を見送ろう
喪主を誰がやるかについて、法的な決まりはありませんが、一般的には故人様の配偶者、次に血縁関係の近い方が務めることが多いです。
喪主の決め方では、故人様との関わりの深さや今後の供養を続けられるかどうかも重要な判断基準となります。
喪主の役割は葬儀の準備から当日の進行、そして葬儀後の対応まで多岐にわたります。
一人で抱え込みすぎず、葬儀社のサポートや家族・親族の協力を得ながら進めることで、安心して葬儀を執り行うことができるでしょう。
身だしなみや立ち居振る舞いに注意し、ご遺族の代表として参列者に感謝を伝えることが、故人様を心を込めて送り出すことにつながります。
静岡県の葬儀は、富士葬祭におまかせください。
いざというときに慌てないためにも、葬儀場の見学や事前相談も承っております。