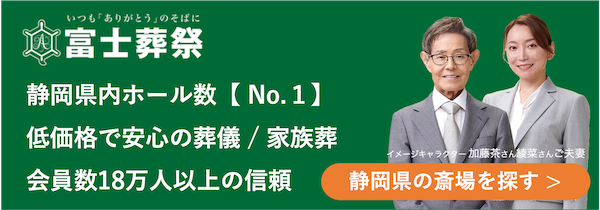BLOGS
葬儀・家族葬ブログ

参列者の知識
葬儀の焼香のやり方はどうする?作法やマナーを紹介
こんにちは。静岡の葬儀社 富士葬祭です。
葬儀で行われる焼香。
久しぶりに葬儀に参列した際に、焼香をどのように行えば良いかわからなくなって慌ててしまった…という経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
いざというときに慌てないためにも、葬儀に参列する前に焼香のやり方を確認しておくと安心です。
今回は、葬儀の焼香のやり方についてお話しいたします。
焼香の意味や目的、マナーなどもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

葬儀の焼香の意味とは?
葬儀で行われる焼香とは仏教の儀式です。
抹香(まっこう)を香炉に落とし、香りを立てることで、仏様や故人様への敬意を示します。
使用する抹香の形や作法は宗派によって異なります。
焼香にはいくつかの目的があります。
まず、香りが浄土の象徴とされ、その香りが周囲に広がることで故人様の冥福を祈るとともに、焼香をする人自身の穢れ(けがれ)を落とし、清浄な心を保つといわれています。
抹香の香りが心身を落ち着かせ、静かな気持ちで儀式に臨むための準備を整えます。
葬儀の焼香の基本のやり方をご紹介

焼香時は、抹香を右手の親指と人差し指、中指の3本でつまみ、額へと近づけます。
この動作を「おしいただく」といい、抹香を目の位置よりも高く掲げるのがポイントです。
焼香の作法は宗教や宗派によって異なります。
- 真言宗:右手の3本の指で抹香をつまみ、おしいただく。焼香は3回
- 天台宗:右手の3本の指で抹香をつまみ、おしいただく。焼香は1〜3回
- 浄土宗:右手の3本の指で抹香をつまみ、おしいただく。焼香の回数に決まりはなし
- 浄土真宗:おしいただかずに抹香を香炉に落とす。焼香は1〜2回
- 臨済宗:おしいただかずに抹香を香炉に落とす。焼香は1回
- 曹洞宗:1回目だけ右手の3本の指で抹香をつまんでおしいただき、2回目はおしいただかない。焼香は2回
- 日蓮宗:右手の3本の指で抹香をつまみ、おしいただく。焼香は1回または3回
葬儀に参列する前に、宗派を確認しておくと良いでしょう。
ただし、参列者ご自身の信仰している宗派がある場合は、そちらのやり方で焼香をしても問題はないとされています。
また、葬儀の時間が限られている場合は、焼香の回数を指定されることもあります。
焼香は故人様のことを偲ぶ気持ちが大切なので、回数は特にこだわらないとする僧侶の方も多くいらっしゃいます。
焼香の種類別の基本のやり方
ここでは、葬儀の焼香の基本のやり方をご紹介します。
焼香では、主に「立礼焼香」「座礼焼香」「回し焼香」があります。
立礼焼香
立礼焼香(りつれいしょうこう)は、椅子席のある式場でよく行われる焼香方法です。
- 順番が来たら席を立ち、焼香台に向かって進む
- 祭壇の前で遺族に一礼し、遺影に向かっても合掌して一礼する
- 焼香台の香炉から抹香をつまんでおしいただき、香炉に落とす(宗派により回数は異なる)
- 再度、遺影に合掌して一礼し、遺族に一礼して席に戻る
座礼焼香
座礼焼香(ざれいしょうこう)は、畳敷きの会場でよく行われる形式で、座ったまま焼香を行います。
- 焼香の順番が来たら、中腰で焼香台の前に進む
- 遺族に一礼してから、遺影に向かって合掌して一礼する
- 焼香台の香炉から抹香をつまんでおしいただき、香炉に落とす(宗派により回数は異なる)
- 再度、遺影に合掌して一礼し、遺族に一礼して席に戻る
回し焼香
回し焼香は、香炉を順番に回しながら行う形式で、会場が狭い場合に用いられます。
- 近くの人から香炉が回ってきたら、軽く一礼して両手で受け取る
- 香炉を自分の前に置き、遺影に向かって合掌する
- 焼香台の香炉から抹香をつまんでおしいただき、香炉に落とす(宗派により回数は異なる)
- 再度、遺影に合掌して一礼し、次の人に香炉を渡す
遺族や親族が焼香を行う場合のやり方も参列者と同じです。
ただし、遺族や親族の場合は遺族へ礼はせず、遺影と僧侶に一礼しましょう。
葬儀の焼香のマナー
葬儀の焼香時には、いくつかのマナーがあります。
数珠
焼香の際、数珠は必須ではありませんが、持参することがマナーとされています。
なお、数珠は個人のものとして使用するものであるため、貸し借りは避けましょう。
手荷物
焼香では両手を合わせるため、手荷物を持たないのがマナーです。
荷物がある場合は足元に置くか、小脇に挟みます。
大きな荷物は事前にクロークに預けると良いでしょう。
焼香のみの参列
葬儀に最後まで参加するのが難しく、焼香のみの参列となること自体は失礼には当たりません。
お通夜や告別式の開式前に伺い、焼香を行います。
焼香後は、喪主や遺族へ「ご愁傷様です」などお悔やみの言葉をかけましょう。
「死ぬ」「終わる」など生死や不吉を連想させる忌み言葉など、葬儀の場で使ってはいけない表現や言葉を事前に確認しておくことも大切です。
なお、葬儀のマナーは地域によっても異なります。
静岡の葬儀のしきたりについては下記コラムでご紹介していますので、あわせてご覧ください。
葬儀の焼香のやり方は事前に確認しておくと安心
葬儀で行われる焼香は仏教の儀式の一つで、抹香を香炉に落とし香りを立てることで、仏様や故人様への敬意を示します。
焼香には、故人様の冥福を祈り、香りが浄土を象徴することから、その広がりが心身を清浄に保ち、仏様の慈悲が行き渡る意味があります。
焼香の方法は宗派によって異なりますが、故人様を偲ぶ気持ちがあればやり方は問わないと考える僧侶の方は多いです。
ほかに、焼香のやり方には立礼焼香、座礼焼香、回し焼香などがあります。
焼香時は数珠を持参することが望ましいとされています。
また、焼香の邪魔にならないよう、手荷物は足元に置くか、クロークに預けるのがマナーです。
静岡県の葬儀は、富士葬祭におまかせください。
いざというときに慌てないためにも、葬儀場の見学や事前相談も承っております。