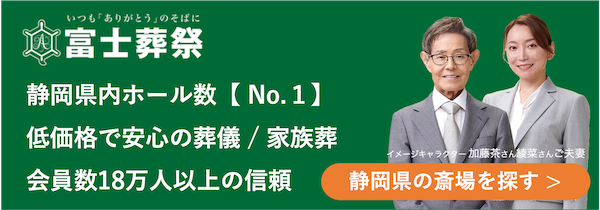BLOGS
葬儀・家族葬ブログ

参列者の知識
葬儀で数珠は必要?数珠の種類やマナーを解説
こんにちは。静岡の葬儀社 富士葬祭です。
葬儀に参列する際、「数珠は必ず必要なのか」「どんな数珠を選べばいいのか」と悩まれる方も多いのではないでしょうか。
今回は、葬儀における数珠の必要性や種類、正しい持ち方やマナーについて詳しくご説明します。
突然の参列でも慌てることのないよう、基本的な知識を押さえておきましょう。

目次
葬儀に数珠は必要?
仏教の葬儀では、数珠を持つことは伝統的なマナーとして定着しています。
ただし、数珠(念珠)はもともとお経を唱える際に用いる仏具であり、参列者が必ず持参しなければならないものではありません。
しかし、参列者にとって数珠は必須ではないものの、日本の葬儀では慣習としてほとんどの方が持参します。
数珠の意味と役割
数珠は単なる装飾品ではなく、仏教において大切な意味を持つ仏具です。
数珠の珠の数は人間の煩悩を表す108個が基本。
仏教では、この108個の珠に「煩悩を消滅させる」という願いが込められているとされています。
また、数珠には厄除けの意味が込められており、持ち主を守る大切な仏具として扱われています。
数珠を購入できる場所
数珠は、仏具店や百貨店の仏具売り場で購入することができます。
最近では、通販サイトなどでも販売しており、家にいながらお好みの数珠を選ぶことが可能です。
また、コンビニエンスストアなどでも取り扱っている場合があります。
なお、100円ショップなどで取り扱っている簡易的な数珠は、ご家族様にあまり良い印象を与えない可能性もあるため、できれば避けたほうが無難です。
葬儀で必要となる数珠の種類
数珠にはさまざまな種類があり、宗派や性別によっても使い分けられています。
数珠の種類による特徴や違い、使い分け方などについてご紹介します。
片手数珠と本式数珠の違い
数珠は大きく分けて、片手数珠(略式数珠)と本式数珠の2種類があります。
片手数珠は、宗派を問わず使用できる一重タイプの数珠です。
携帯しやすい一連のタイプで、54玉や27玉などの珠数があります。
一方、本式数珠は宗派ごとに仕立てられた数珠で、玉の形や数珠の長さなどは宗派によって異なります。
例えば、浄土宗では二連の輪違いで玉の数は108より少ない、天台宗では平玉が使われている、真言宗では四天という小さい玉が含まれるなど。
ただし、葬儀へ参列時に、故人様の宗派に合わせて数珠を直す必要はありません。
宗派による数珠の違いはマナー違反とならないため、ご自身の宗派の本式数珠を持参するか、略式の片手数珠を使用しましょう。
男性用・女性用の違い
数珠は性別によって珠の大きさが異なります。
男性用は10~12mm、女性用は6~8mmと、女性用の方が一回り小さいのが一般的です。
房の色に決まりはありませんが、男性は青や緑、茶色など落ち着いた色を、女性はピンクや紫など優しい色合いを選ぶ方が多いようです。
子ども用の数珠
子ども用の数珠も販売されており、小さな手のサイズに合わせて作られています。
子ども用は壊れにくい素材でできており、カラフルなものが多いのが特徴です。
ただし、幼い子どもは数珠を丁寧に扱えない可能性もあるため、無理に持たせる必要はありません。
数珠を大切に扱えるようになってから準備することをおすすめします。
葬儀の数珠のマナーを確認

葬儀の数珠のマナーについて、主なものを確認しておきましょう。
基本的な持ち方
片手数珠の基本的な持ち方は2通りあります。
1つ目は、左手の親指と人差し指の間に輪をかけ、親指が輪の外側に出るようにして持ちます。
右手を合わせて合掌し、房は自分から遠い側に向けて下に垂らします。
2つ目は、合掌した両手の親指と人差し指の間に輪をかけ、親指が輪の外側に出るようにして持ちます。
房は自分から遠い側に向けて下に垂らします。
また、基本的に数珠は、葬儀が行われている間は常にカバンから出しておくのがマナーです。
袱紗で包んで持ち歩き、葬儀中は左手首に数珠をかけておきましょう。
焼香時の作法
焼香の際は、以下の手順で数珠を使用します。
- 左手に数珠をかけた状態で焼香台へ向かう
- ご遺族様と僧侶に一礼する
- 左手の親指と人差し指の間に輪をかけるように持つ
- 右手で焼香をする
- 両手の親指と人差し指の間に数珠をかけて合掌する
焼香の作法については、こちらのコラムもご参考ください。
数珠を忘れた場合の対処
急な参列で数珠を忘れてしまった場合でも、慌てる必要はありません。
まずは葬儀会場や近くのお店で購入できないか確認してみましょう。
葬儀会場によっては、売店などで販売している場合もあります。
また、葬儀社のスタッフに相談してみても良いでしょう。
ただし、数珠は持ち主の分身とも考えられているため、数珠の貸し借りは望ましくありません。
葬儀の持ち物やマナーについて、より詳しく知りたい方はこちらのコラムもご覧ください。
数珠のお手入れ方法
数珠を長く大切に使うためのお手入れ方法をご紹介します。
数珠の使用後は、柔らかい布で優しく汚れを拭き取ります。
夏場は汗が付着しやすく、特に高価な数珠は汗で変色する可能性があるため注意が必要です。
房は、必要に応じてくしで軽くとかしておきます。
保管時の注意点
数珠は桐の箱や袱紗に包んで保管するのが基本です。
木製の数珠は虫食いの可能性があるため、防虫剤を入れて保管しましょう。
数珠が切れてしまったら
数珠の糸は経年劣化で切れることがあります。
これは悪縁が切れたという意味で、決して不吉なことではありません。
きれいな白い紙に包んでお寺にお返しするか、仏具店に処分を依頼しましょう。
高価な数珠は、販売店で修理も可能です。
葬儀には数珠がマナーとして必要なものの、必須ではない
葬儀における数珠は、参列者にとって必須ではないものの、マナーとして持参することが望ましい持ち物です。
片手数珠か本式数珠か、また性別によって適切なものを選びましょう。
数珠は持ち主の分身とも考えられており、貸し借りは避け、丁寧に扱うことが大切です。
基本的な作法やマナーを理解し、故人様への弔意を表す際に失礼のないよう心がけましょう。
静岡県の葬儀は、富士葬祭におまかせください。
いざというときに慌てないためにも、葬儀場の見学や事前相談も承っております。