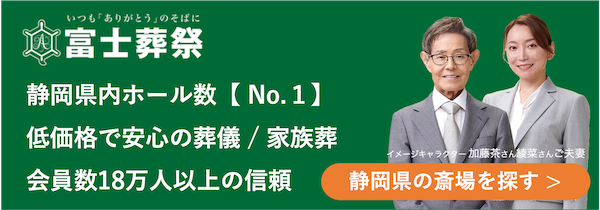BLOGS
葬儀・家族葬ブログ

参列者の知識
葬儀の弔辞とは?書き方から読み方、マナーまで詳しく紹介
こんにちは。静岡の葬儀社 富士葬祭です。
葬儀で弔辞(ちょうじ)の依頼を受けると、「何をどのように話せば良いのだろう」「読むときに気をつけることはある?」といった戸惑いや疑問が生じることもあるでしょう。
弔辞は、故人様との最期のお別れの言葉であると同時に、ご遺族の心に寄り添う大切な役割も担っています。
本コラムでは、弔辞の意味から書き方、当日のマナーに至るまでをわかりやすくご紹介します。
故人様との思い出を振り返りながら、心のこもった弔辞を準備する際の参考になれば幸いです。

目次
葬儀の「弔辞」は故人様へのお別れの言葉
弔辞(ちょうじ)とは、葬儀や告別式の場で故人様に向けて述べる追悼の言葉のことです。
主に、生前に深いご縁のあった方が、霊前で最後の想いを語ります。
弔辞を読むのは、故人様と特に親しかった方が選ばれることが多く、例えば以下のような関係の方が挙げられます。
- 学生時代からの旧友
- 職場の上司、同僚、または部下
- 教え子や恩師
- 趣味などを通じた交友のある方
- お孫さんなどご家族の一員
弔辞を述べる人数は葬儀の規模によって異なりますが、一般的には1~3名、多くても5名程度が目安です。
弔辞は、故人様への敬意と感謝を表すとともに、参列者やご遺族にとっても慰めや癒しとなる大切な時間です。
依頼を受けた際は、特別な事情がない限り、謹んでお引き受けするのが礼儀とされています。
ご遺族の「この方にお願いしたい」というお気持ちを大切に受け止めましょう。
葬儀での弔辞を依頼された際の書き方と例文
弔辞を書く際は、構成を意識することで、想いを丁寧に伝えることができます。
以下のような流れを参考にすると、文章がまとまりやすくなります。
- 冒頭: 故人様への呼びかけ、関係性の紹介
- 訃報を知った時の気持ち: 驚きや悲しみの感情を素直に綴る
- 思い出やエピソード: 故人様との印象深い出来事や人柄を伝える
- 現在の想いと今後の決意: 感謝や故人様への想い、今後の姿勢など
- 結びの言葉: 冥福を祈る言葉で締めくくる
弔辞は3分程度、文字数で800~1,200文字ほどが目安です。
複数人で弔辞を述べる場合は、持ち時間が長くなりすぎないよう調整が必要です。
弔辞の例文
以下に、関係性別の弔辞の例を紹介します。
友人としての弔辞
◯◯さんの御霊前に、心からお別れの言葉を申し上げます。
突然の訃報を受け、まだ現実を受け入れられずにいます。
◯◯さんとは大学時代からの友人で、社会人になってからも定期的に連絡を取り合っていました。
明るく、前向きな人柄で、私が悩んでいるときには励ましの言葉をくれました。
仕事に行き詰まった際も、「きっと道は開けるよ」と支えてくれたその一言が、今でも忘れられません。
◯◯さんとの大切な思い出を胸に、これからも前を向いて歩んでまいります。
どうか安らかにお眠りください。
部下としての弔辞
◯◯部長の霊前に、社員を代表してご挨拶申し上げます。
突然のご訃報に、私たちは深い悲しみに包まれています。
◯◯部長は常に部下を気遣い、温かい指導をしてくださいました。
厳しさの中にも思いやりがあり、私たちは大きく成長することができました。
新人の頃、失敗した私に「それも経験だ」と優しく声をかけてくださったことを今でも覚えています。
部長の教えを胸に、これからも社員一同、会社の発展に尽力してまいります。
心からの感謝とともに、どうぞ安らかにお眠りください。
孫としての弔辞
おじいちゃん、突然のお別れに、まだ気持ちの整理がついていません。
子供の頃、私の話をいつも真剣に聞いてくれた優しい笑顔が思い出されます。
夏休みに遊びに行くたびに、私の好きな料理を用意して待っていてくれたことも忘れられません。
おじいちゃんの優しさを胸に、これからしっかりと歩んでいきます。
今まで本当にありがとう。安らかにお休みください。
弔辞を書く際は忌み言葉に注意を

葬儀の弔辞を作成する際には、「忌み言葉」に十分な注意を払う必要があります。
忌み言葉とは、葬儀の場において縁起が悪いとされる表現や、不幸が繰り返されることを連想させる言葉のことです。
忌み言葉の主な例
以下に代表的な忌み言葉をご紹介しますので、弔辞においては使用を避け、別の表現に置き換えるよう心がけてください。
重ね言葉
「たびたび」「くれぐれも」「重ね重ね」「次々」「ますます」「度々」など。
これらは不幸が重なることを連想させるため、不適切とされます。
死に直結する言葉
「死ぬ」「死去」「急死」といった直接的な表現は避け、「逝去」「永眠」「他界」などに言い換えます。
ネガティブな印象を与える表現
「苦しむ」「切る」「離れる」「浮かばれない」なども、ご遺族に配慮し避けることが望まれます。
忌み数
「四(死)」「九(苦)」といった数字は忌避される傾向があります。
必要な場合には「よっつ」「ここのつ」などと読み換えます。
宗教ごとの表現への配慮
故人様の宗教によって、適切な表現も異なります。
代表的な宗教における弔辞の結びの表現例は以下のとおりです。
- 仏教:「ご冥福をお祈りします」「成仏されますように」など
※ただし、浄土真宗では「臨終即往生」という考え方のため、「ご冥福を祈る」という表現は使わず、「謹んで心よりお悔やみ申し上げます」を使用します - 神道:「御霊(みたま)の安らかならんことをお祈りいたします」
- キリスト教:「天に召され、安らかなる眠りにつかれますように」など
事前にご遺族に確認を取るか、宗教儀礼の形式に沿った表現を選ぶようにしましょう。
葬儀での弔辞の読み方とマナー
弔辞を読み上げる場面は、葬儀の中でも非常に厳粛な時間です。
当日に慌てることのないよう、あらかじめ準備を整えておきましょう。
原稿の形式と事前準備
正式なスタイルでは、奉書紙や巻紙に薄墨で縦書きするのが伝統的ですが、最近では便箋に万年筆や黒インクのペンで丁寧に書いた略式でも問題ありません。
ただし、どの形式であっても、以下の点にして準備しましょう。
- 丁寧で読みやすい文字で記す
- 難しい漢字にはふりがなをつける
- 3分程度に収め、声に出して練習しておく
十分な準備を行うことで、当日も落ち着いて臨めるでしょう。
弔辞を読む際の所作
厳粛な儀式であることを理解し、礼を尽くした所作を心がけましょう。
- 司会者に名前を呼ばれたら静かに起立し、祭壇の前へ進む
- 僧侶、ご遺族、遺影の順に一礼する
- 弔辞の包みを取り出し、丁寧に文面を開く
- 包みは懐または台に置き、原稿は両手で持って読み上げる
- 読み終えたら再び包み、表面を霊前に向けて供える
- 再度、遺影・僧侶・ご遺族に一礼し、席に戻る
声のトーンと読み方の注意点
弔辞を読み上げる際には、聞き取りやすく、丁寧で落ち着いた口調を心がけます。
会場にしっかりと届くような適度な声量で、早口にならないよう意識しましょう。
緊張で声が詰まってしまうことがあっても、深呼吸してから再開すれば問題ありません。
言葉の一つひとつに想いを込めて、故人様への敬意と感謝が伝わるような朗読を心がけましょう。
葬儀の弔辞は、故人様に贈る最後の心からの言葉
弔辞は、故人様に贈る最後の言葉であり、ご遺族への慰めの役割も果たす、大変意義深いものです。
形式に沿って心を込めた内容を丁寧に綴り、忌み言葉を避けつつ、故人様との思い出や感謝の気持ちを明確に表現しましょう。
また、弔辞を朗読する際には、適切な所作・声のトーン・読み方のマナーを守ることで、故人様への敬意、ご遺族や参列者への配慮がより伝わります。
万全の準備を整え、真摯な気持ちで臨む弔辞は、故人様への最良のはなむけとなるでしょう。
静岡県の葬儀は、富士葬祭におまかせください。
いざというときに慌てないためにも、葬儀場の見学や事前相談も承っております。